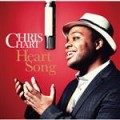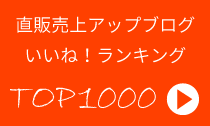ブランディングとマーケティングは、似たような作業です。ブランディングは、他との違いを際立たせて相手に認知してもらうこと。マーケティングの捉え方によって、主従関係が逆転します。
1)マーケティングのツールとしてのブランディング
モノやサービスを創って売るすべてのプロセスをマーケティングの作業と考えると、ブランディングはマーケティングのひとつのプロセスです。
2)マーケティングを不要とするブランディング
売り込まなくても売れていく状態を創る。これが究極のマーケティングの姿です。ブランディングがしっかり構築されていれば、このいわばマーケティング不要の状態に近づけるわけです。
モノやサービスは、その機能だけでヒトが買うか買わないか判断しているわけではありません。ブランドの違いが少なからず影響しています。
たとえば、にんにく。八百屋にいって中国産のにんにくと青森産のにんにくの価格差に驚いた人は少なくないはずです。
中国産にんにく、10個入りネット=200円。
青森産にんにく、1個=200円。

見た目にほぼ同じにんにくが、中国ブランドと青森ブランドで10倍の値段差があります。
中国産だからすべてが質が悪いわけでもないですし、
青森産だから100%安全なわけでもないでしょう。
ただ食べてみると、味の差は歴然としています。
買うときに、そのにんにくの味を確認してから買うことはできません。今までの経験と照らしあわせて、用途と懐と相談しながら、どちらか選ぶ。または八百屋のおじさんが、「今日の青森のにんにくは上物だよ」という一言を信頼するという選び方もあります。いずれにしても、にんにくそのものの質ではなく、付帯的な情報が選択の頼りになります。これがブランドです。
青森県田子町は、はやくからにんにくの町としてのブランディングに取り組んできました。狙いは、
青森産にんにく、1個=200円。
青森県田子産にんにく 1個=300円。
というような状態をつくることです。
1993年に田子町ガーリックセンターを設立。年間2万3000人が訪れる人気施設。にんにくせんべい、にんにくカレーはいいとして、にんにくソフトまであります。町の街灯はにんにくの形です。
「田子」という名前が買う人に認知されない限り、有効なブランドになりません。そのため田子町は手を変え品を変え、にんにくにまつわる面白い情報を発信し続けています。もちろん品種にはこだわって、質の追求を怠りません。ブランディングは地道な積み重ねで構築されるものです。また壊れるのも一瞬という怖さもあります。
田子町の姉妹都市であるアメリカカリフォルニアのギルロイ市。全米有数のにんにくの産地です。
TPPで、
アメリカギルロイ産安心にんにく 1個50円。
というポジションのブランディングがもし構築されたら、、、
田子町もうかうかしていられません。
直販売上アップ請負人!直販コンサルのPlus2
MENU
直販売上アップブログ